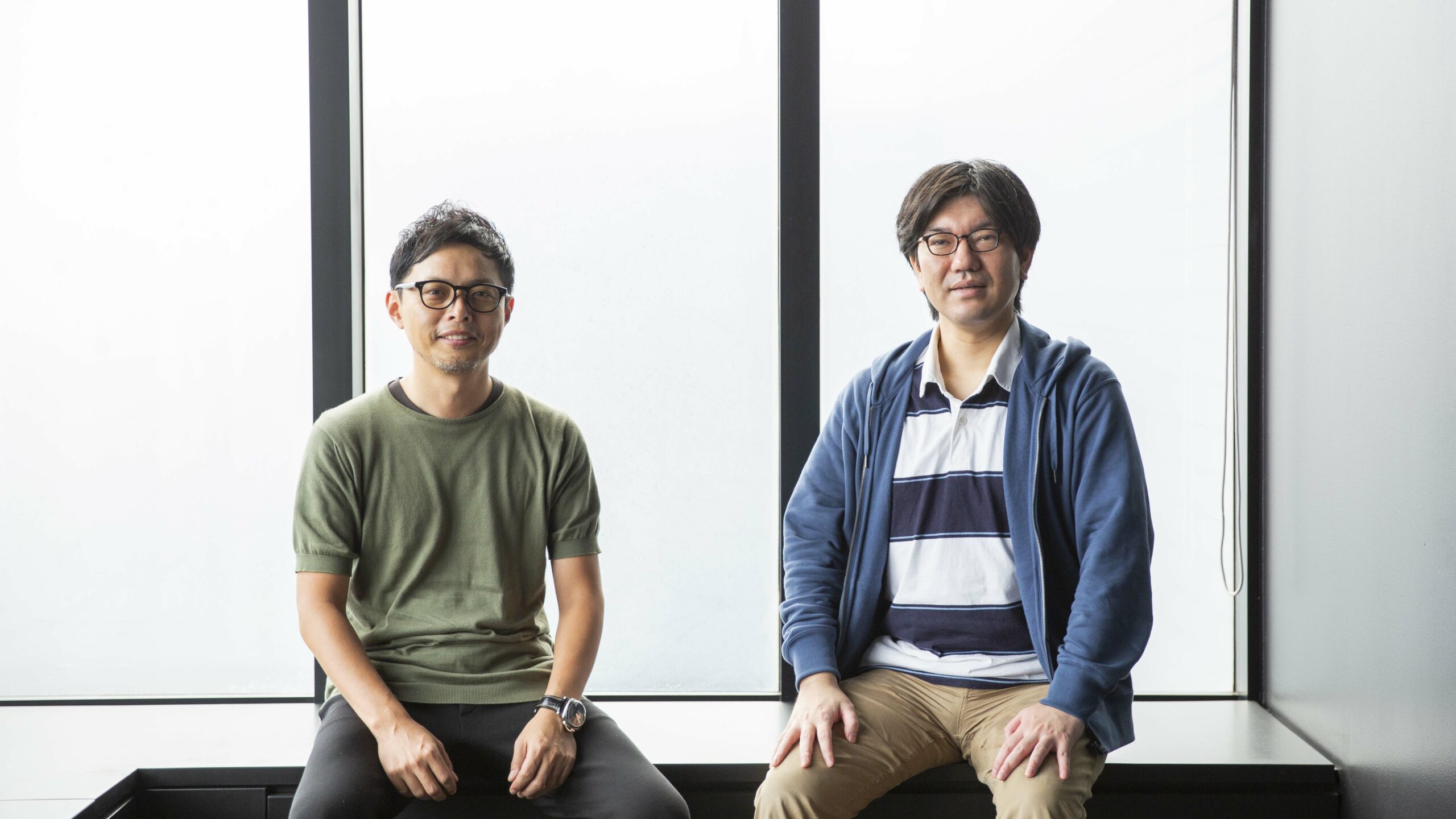2021.08.06
DXの本質は「業務改善」ではなく「ワクワクする未来」にある

ITの未来を語るうえで、避けて通れない「デジタルトランスフォーメーション(DX)」。業務効率化や新規ビジネス創出、先端技術活用などその内容は多岐にわたり、取り組みを進めている企業も少なくありません。
しかし、思ったように業務が改善しない、現場の協力が得られない、そもそもどこから手を付けたら良いかわからない……。「こんなはずではなかった」という声があることも事実です。なぜ日本のDXは、思うように進まないのでしょうか?
今回は、株式会社プラネットプラン代表取締役であり、慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科 特任教授でもある須藤実和氏に、DXに関する悩みを解決するヒントを伺いました。聞き手はトレノケート取締役の杉島泰斗です。
取材先のプロフィール

須藤 実和(すとう みわ)氏
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
株式会社プラネットプラン 代表取締役
東京大学理学部生物化学科卒業、同大学理学系大学院修士課程修了。博報堂におけるマーケティング戦略立案経験、アーサー・アンダーセンにおける監査、買収監査(due diligence)経験を経たのち、シュローダー・ベンチャーズに参画、ベンチャー企業投資育成業務に携わる。1997年、戦略系経営コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーに参画し、2001年より同社パートナーとして顧客企業のコンサルティング活動に加えて幅広い講演・執筆活動を行う。現在は、教育活動やベンチャー企業の育成支援活動に携わるとともに、国内大手企業の経営支援、人材開発支援に従事している。公認会計士。
インタビュアー

杉島 泰斗(すぎしま たいと)
トレノケートホールディングス 代表取締役社長
熊本県出身。東京工業大学を卒業後、SCSデロイトテクノロジー、不動産ポータルサイトLIFULL HOMES、株式会社クリスク 代表取締役を経て現職。
INDEX
目次
DXの本質は「業務改善」や「業績向上」ではない
DXを進めなかった企業は顧客から選ばれなくなる
「プチキャリア経験」が社内のDXを前に進める
DXの本質は「業務改善」や「業績向上」ではない
杉島
DXという言葉が叫ばれて久しいですが、「DXってなに?」という問いに正面から答えることは簡単ではないと感じます。そもそも、社員や経営者など立場によってDXの理解も違っているのではないでしょうか。
須藤
おっしゃる通りですね。業務効率化がDXだと思っている方もおられますし、SNSで広告宣伝をすることがDXだと思っている方もいる。理解がバラバラなんですね。「DX戦略室」みたいな組織を作って勉強をしてみても、ちょっと実証実験をやって、そこで終わりになってしまったり……。

須藤実和(すとう・みわ) 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授。株式会社プラネットプラン 代表取締役。 現在は、教育活動やベンチャー企業の育成支援活動に携わるとともに、国内大手企業の経営支援、人材開発支援に従事している。
杉島
理解がバラバラのまま、「とりあえずやってみよう」と着手しても、なかなかうまくいきませんよね。ゴールが見えていないわけですから。
須藤
そうですね。「DXで会社の未来がこう変わる」というゴールを提示しないと、社員の足並みが揃いませんし、協力も得られないでしょう。そもそもDXの本質は「新しい顧客価値の創造」にありますから。
杉島
DXで新しい顧客価値の創造できている事例があれば、教えていただけませんか?
須藤
最近面白いなと思ったのは「バーチャル伊勢丹」ですね。三越伊勢丹ホールディングスが、VRアプリ内に伊勢丹新宿店の仮想店舗を作ったんです。自分のアバターが店舗を散策して、実際にネットショップで買い物もできます。
この仕組みがどんどん進化すれば、店員さんと会話しながら買い物ができたり、仕事の休み時間にアバターとして買い物に行ったり、顧客体験の幅が広がりますよね。「伊勢丹は小売業界の未来をこう考えている」というメッセージにもなりますし、社員にとってもDXのゴールをイメージできる。こうした「未来へのワクワク」が、DXを前に進めるのだろうと思います。
杉島
なるほど。確かに「業務改善で売上を何%上げる」という数値目標がゴールでは、経営者しかワクワクしませんから……。

杉島泰斗(すぎしまたいと) トレノケートホールディングス 代表取締役社長 熊本県出身。東京工業大学を卒業後、SCSデロイトテクノロジー、不動産ポータルサイトLIFULL HOMES、株式会社クリスク 代表取締役を経て現職。
須藤
そうですね(笑)。トップだけがワクワクしては、社員はDXを自分ごととして考えられないでしょう。「経営陣がまたなにかやってるな」と思うだけで。
杉島
一般的にDXは業務効率化を目的にすることが多いですよね。でもそれは「社内」が目的地であって、本質である「新しい顧客価値の創造」は「社外」が目的地にある。ベクトルが逆なんですね。
須藤
トップから「DXで業務を効率化する」と言われると、現場は「いまも頑張っているのにまだ足りないの?」と感じると思うんです。DXが「やらされるもの」になってしまう。未来が提示されなければ、なおさらそう感じるでしょう。
ワクワクする未来がなければ、自発的なエネルギーも湧いてきません。DXの本質を取り違えた結果、社員が本来持っている力を活かせないのは、とてももったいないことだと思います。
DXを進めなかった企業は顧客から選ばれなくなる
杉島
特に日本は、DXに対する取り組みが遅れていると言われています。これはなぜなのでしょうか?
須藤
日本はアナログな経営プラットフォームの上で、盤石な組織モデルを築いてきました。逆にこのことが、DXにとって裏目になっているのではないでしょうか。
製造業の「すり合わせ技術(※)」に代表されるように、相手の領域まで考えたうえで自分の仕事をこなすことが、日本企業の強みのひとつでした。「あうんの呼吸」による連携で、生産効率や品質を高めていたわけですね。
※製品を構成する部品や材料を、精密な調整することによって、本来の性能を発揮させること。
須藤
ただ、この「あうんの呼吸」を、そのままデジタルの経営プラットフォームに移すのは難しい。
雑にデジタル化してしまうと、その強みはなくなってしまいますから。
さらに次世代を担う若い世代にとって、前提となる文脈が必要な「あうんの呼吸」は、空気を読まないと怒られる「暗黙のルール」であり、働きづらさにつながりかねません。
杉島
はっきり言ってくれないとわからない、ということですね。リモートワークが当たり前になったいま、なおさら組織の空気を読むのは難しいでしょうし……。
須藤
逆に考えれば、「若い世代が働きやすいと感じる環境」が、デジタルの経営プラットフォームを推進するヒントになるのではと思います。
経営者と若い世代がディスカッションする機会を持てば、ここがDXの障壁になっているのか、と気づけるでしょう。若い世代がどんな会社を「クール」(カッコいい!)と感じるかをつかめば、旧来の発想から飛躍できるはずです。
杉島
若手社員に寄り添うことができれば、若い世代の顧客にも寄り添える気がします。最近、docomoが新料金プラン「ahamo」を打ち出しましたよね。代理店での対面契約からネット契約へのDXは、まさに若い世代に向けて新しい顧客価値を創造したものではないですか。
須藤
その通りですね。もしdocomoも「ahamo」を作らなかったら、次の世代に関心を持たれないブランドになったかもしれません。極論を言うと、「DXを進めなかった企業は選ばれなくなる」と思うんです。
杉島
「DXなんて自分には関係ない」と思っていると、手遅れになってしまうと。
須藤
コロナ禍で、DXはますます待ったなしのものになっています。マイクロソフトCEOのサティア・ナデラ氏も、2020年の決算説明会で「(コロナ禍の)この2カ月で2年分に匹敵するDXが起こった」と述べていました。次世代にも選ばれる会社でありたければ、経営者にはDXに取り組まないリスクについて敏感であってほしいですね。
「プチキャリア経験」が社内のDXを前に進める
杉島
これまで経営者の意識についてお話いただきましたが、現場レベルの話もお聞かせいただければと思います。気になっているのは、IT人材の不足です。経済産業省の試算によれば、現在は需要に対して約30万人が不足しており、2030年には約80万人不足すると言われています。「2025年の崖(※)」まで、残された時間は多くありません。
※2025年の崖:経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で使用された言葉。IT人材不足によってDXが進まなければ、既存の基幹システムを見直すことができず、2025年以降に最大で約12兆円の経済損失が発生するという。
須藤
IT人材が不足すれば、IT部門にかかる負荷はますます重くなりますよね。IT技術が進化し、便利になった一方、セキュリティーなどの「守り」はより重要になっていますから。
杉島
確かに、保守運用やトラブルシューティング、社員のITサポート、予算管理など、IT部門が「守り」を担っている部分は大きいですね。
須藤
本来はDX推進などの「攻めのIT」をリードする立場でもあるのに、「守り」にリソースを割かれているわけです。ただでさえ人が足りない大変な状況なのに、さらに「DXをやるぞ」と言われても、なかなか前向きになれないのではと思います。
杉島
ではもし「攻めのIT」が可能な状況だとしたら、IT部門にはどんな活躍を期待されますか?
須藤
DXでこんなことが可能になる、と社内に啓蒙する、「伝道師」の役割であってほしいですね。IT部門がビジネス課題とITの橋渡し役となれば、部門間で新たな化学反応が起こることも期待できます。人材不足のなか、簡単なことではありませんが……。
杉島
それでもDXに真剣に取り組むならば、まずはどこから始めればよいでしょうか?
須藤
ビジネスサイドとIT部門の、相互理解から始めてみるのはいかがでしょうか。
研修などの機会を通じて、ビジネスサイドの人がプログラムを動かす経験をしてみる。また、IT部門の人もビジネスを作る面白さを感じてみる。相手の分野について知れば、「もっとこうしたらいいのでは」という発想も生まれてくると思うんです。
杉島
化学反応の第一歩、というわけですね。
須藤
「もっとこうしたらいいのに」は、よその会社に対してはよく感じているはずなんです。「この店、もっとこうしたらいいのに」とか、「このシステム、もっとこうだったらいいのに」とか。でも、自分の会社のことになると、あんまり口を出さないじゃないですか。
杉島
わかります。よその会社のことになると、いいアイデアが出ますよね(笑)
須藤
「こうだったらいいのに」はひとつの未来です。相互理解を進めれば、社内でも未来について話し合える環境になるはず。ダブルキャリアまでいかなくても、「プチキャリア経験」をすることで、新たに見えてくるものがあるのではないでしょうか。
(取材・執筆:井上マサキ 撮影:小野奈那子 編集:鬼頭佳代/ノオト)